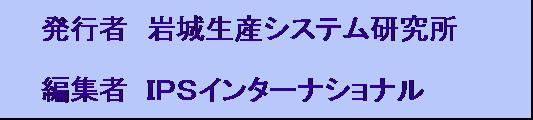連載コラム
| 第173号 | 「工程の考え方」 | 岩城生産システム研究所 | 岩城 康智 |
物を生産する上で、複数の工程が必要ですが、それぞれの工程をどのように繋いでゆくのかは、リードタイムのみでなく、コスト、品質をより良くする上で重要になります。
各工程においても加工時間に目を向けると。
1、 セット時間 (ワークを治具等にセットする+ワークを治具から外す作業時間)通常は治具上に前のサイクルに加工されたワークが載っているはずですから、ワークを外す+外したワークを一時置きすると言う作業が発生します。これは治具の数だけ発生することになり、作業を非常に煩雑にするので、必ず治具からは自動的に外れ、次のワークがセット出来るようにする必要があります。(自動払い出し)また、セット時おいても、固定する必要がある場合は、手動でクランプをしたり、または手で押さえなくてはならないような治具は改善が必要と言えるでしょう。通常1部品あたり1、5から2秒が好ましく、これが出来るように部品の置き方、治具の位置/高さを決めてください。
2、 ツールの移動時間 (刃具若しくは工具の移動時間の事で、加工工具がワークに当たり実際の加工が始まるまでの時間+加工が終わり刃具が定位置に戻り、治具からワークが外せるようになるまでの時間)しばしば、ツールの移動時間はおざなりにされやすいのですが、ここでの移動は行きと帰りがあるので、改善効果は2倍になので、ミリ単位で調整が必要です。ネジの供給等でどうしてもストロークが必要な場合はセット時間を利用してみるのも良いと思います。
3、 正味加工時間 (実際に加工している時間)例えばネジを締めるのであるならば、本当の加工時間は締め付けの効く最後の4分の1回転が加工時間です。溶接の場合は実際にアークの発生している時間となります。(火花率)また、計量器の場合は量目を合わせる最後の数パーセントが本当の意味の加工時間となります。このように考えると実際の加工時間は非常に短いのがわかると思います。
4、 ワークの移動時間 (次の工程へワークを移動する時間)次の工程の作業点までの移動時間となりますが、通常では作業者によるハンドワーク時間と言えます。前期にあるような払い出し装置があれば直接次の工程に仕掛ける(直仕掛け)ことになるので作業者のリズムが良くなります。ここの作業は速度が速ければ良いというものではなく、作業をやりやすく、一発で次工程に仕掛けられるように距離を適正に調節するのが肝心です。これらが適正であるならば、1秒前後程度でできるはずです。
このように考えると1完成品あたり30秒程度のタクトであれば、20工程ほどを1人でできる勘定となりますが、実際には検査工程、梱包工程があるのでそのままには行かないのでー。とは言っても2〜3人で行うのはさほど難しくないと思いませんか?