 |
発行者 岩城生産システム研究所 編集者 IPSインターナショナル |
|||
| 平成20年3月15日発行 第062号 | ||||
| ― 目 次 ― | ||||
◆ 「-読者投稿-」 中村 俊一 様 ◆ 「トヨタ生産方式の基本は三本柱が正しい③」 岩城生産システム研究所 岩城 宏一 |
||||
|
|
||||
 「-読者投稿-」 「-読者投稿-」 |
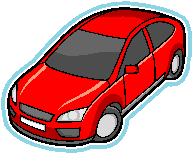 |
|||
| 中村 俊一 様 | ||||
|
|
||||
|
|
||||
 「トヨタ生産方式の基本は三本柱が正しい③」 「トヨタ生産方式の基本は三本柱が正しい③」 |
 |
|||
| ㈱岩城生産システム研究所 岩城 宏一 | ||||
しかし、各工程間の仕掛を減らしてみると、各々が勝手な動きをしている限り、各工程はちぐはぐになり、同期してジャストインタイムに動くことは出来ないことがわかります。即ちジャストインタイムのためには、部品の取り入れから工場の中を通り客先まで、あたかもベルトコンベアーでつないでいるような状態が必要であります。この問題への対応策が言うまでも無く、生産の平準化であります。 このように、生産の平準化は、トヨタ生産方式のジャストインタイムが成立する為の、不可欠な要素であり、また、それは大野先生の常識を遥かに越えた発想と、それを具体化するための不屈な挑戦によって、初めての実現したものでしょう。そのことは、平準化に至るまでの技術的な必然性を追ってみると、容易に想像出来ることであります。以下に生産の平準化に至るまでの、大野先生達の挑戦の一端を辿って見ましょう。 先ず大野先生は、生産効率の最も大きな阻害要因は、生産の変動にあり、そこからいろいろな無駄が発生することを、感じとめていたように思います。事実先生は当時、「無理」「無駄」「むら」の中で、「むら」即ち変動が一番問題だと言っていました。 またその変動は、実際の市場の売れ方の変動によるものと、工場側の造り方の変動の、二つによって発生すること。さらに、工場側の変動は各工程の加工速度の違いによる、停滞品によって発生することを、見抜かれていたように思います。 各工程が加工速度を合わせ、ジャストインタイムに働けば、当然全体の品物の停滞は無くなり、工場側の変動を抑えることが出来ます。そのためには、これまでのように、一度に沢山纏めて造ることを止め、毎日少しずつ造ることが大切であります。これは、当時(現在も)の世の中の常識である、“纏めて造った方が安くなる”とは全く逆の発想であります。 さらに毎日少しずつ造るためには、一台の設備で、多くの種類の品物を加工することが必要であります。この問題を解決するために、当時は半日程度かけて行っていた設備の段取り替えを、僅か数分で出来るように改善しました。 このような並外れの挑戦は、誰もが予想さえできなかったことだと思います。この点は、実際経験した皆さんには、十分理解できることだと思います。 工場の中での変動の要因が取り除かれると、製品の毎月の販売数を平均して毎日生産するように、生産の投入の仕方を変えることが可能になります。それによって、毎日平均して生産されてくる数量と実際に売れる実販売数との差を吸収するだけの微量の在庫(店)によって、外部の変動を完全に吸収出来、工場への変動を抑制することができます。このようにして生産の平準化が完成することになりました。 (つづく) |
||||
| ■無断複製・転用・販売を禁止します■ Copyright©Iwaki Production Systems Research Ltd. 2005- |
||||