 |
発行者 岩城生産システム研究所 編集者 IPSインターナショナル |
||
| 平成19年11月1日発行 第054号 | |||
| ― 目 次 ― | |||
◆ 「自ら考え、そして実行することの大切さ」 富士通メディアデバイスプロダクツ 村石 絹枝 様 ◆ 「コンサルタントのひとりごと 〜全員参加による経営活動の薦め33」 岩城生産システム研究所 岩城 宏一 |
|||
|
|
|||
 「自ら考え、そして実行することの大切さ」 「自ら考え、そして実行することの大切さ」 |
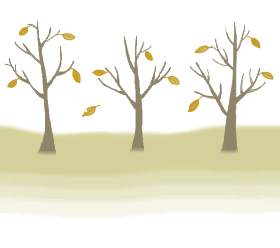 |
||
富士通メディアデバイスプロダクツ株式会社 須坂事業所 生産部 村石 絹枝 様 |
|||
私は生産部に所属しSAWデバイス製品用の部材の手配・調達を担当しています。 岩城先生、松岡先生、そして常駐の清水先生にご指導頂き、3年目に突入した生産革新ですが、今でこそ言葉の意味が少しずつ分かってきたところで、最初は全く言葉の意味が理解できないところからのスタートでした。 先生方にご指導頂くまでは、生産革新を行っている関係会社の指導会に参加させて頂き、自分たちなりに見様見真似の革新を進めていました。 しかし、松岡先生に初めて部材倉庫を見て頂いた時、即座に、『だめ出し』され、それから今に至るまでは無我夢中でやってきたような気がします。 倉庫のレイアウト変更、スペースの削減、棚卸削減(回転在庫は1.5日分)、部材の取り込みは毎日(必要な物を必要な時に必要なだけ)、かんばんとルート便による定時取り入れと、盛り沢山の課題に毎日頭をひねりながら今日に至っています。 |
|||
| 先生方の指導がスタートしてから何回目かの指導会の時、松岡先生に「革新を始めてどうですか?」と聞かれ、とっさに「景色が変わりました。」と答えてしまったことを思い出します。 それまでの部材倉庫とは物量も景色も変わり、今では物を管理しなくても目で見て分かる『ストア』になってきました。 部材調達においては、小口化、定量化、かんばんを使った取り入れなど多くの課題があり、取引先と交渉を進める上でも購買部門の協力が必要不可欠でした。 最初は生産革新への取り組みに温度差があり、お互いが理解するために議論する日が続き中々前に進むことが出来なかったのですが、今では購買部門と連携を図り強力な体制で取引先との交渉に臨んでいます。 それでも私たちが思い描いているように取引先の協力を得ることは難しく、苦心しているところですが、出来ることを少しずつでも見つけて前進していこうと思っています。 |
 |
||
| 生産革新を始めたころは、「そんなの無理だ」「出来ない」と思うことが毎日で、取り組みに対しても後ろ向きだった自分が、今では生産革新の真意が少しずつ分かってきました。それは『出来ないことはいくらでもあげられる。でも、その中で出来ることを考え、そして実行することが大切』だという事です。 これからも先生方のご指導を頂きながら、目標に向けて更なる前進を図っていきたいと思います。 以上 |
|||
|
|
|||
 「コンサルタントのひとりごと」 「コンサルタントのひとりごと」 |
 |
||
| 岩城生産システム研究所 岩城 宏一 | |||
|
|
|||
| ■無断複製・転用・販売を禁止します■ Copyright©Iwaki Production Systems Research Ltd. 2005- |
|||