 |
発行者 岩城生産システム研究所 編集者 IPSインターナショナル |
||
| 平成19年10月01日発行 第050号 | |||
| ― 目 次 ― | |||
◆ 「全員参加によるトヨタ生産方式」 岩城生産システム研究所 清水 誠 ◆ 「コンサルタントのひとりごと 〜全員参加による経営活動の薦め31」 岩城生産システム研究所 岩城 宏一 |
|||
|
|
|||
 「全員参加によるトヨタ生産方式」 「全員参加によるトヨタ生産方式」 |
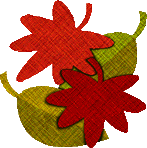 |
||
岩城生産システム研究所 清水 誠 |
|||
トヨタ生産方式を導入し生産革新活動を展開する企業は、生産現場を中心とした改革活動として一般的に受け止められている。 革新活動で真の成果を得ようとするには、全員参加で改革活動を展開しないと『体質の強い企業』には改革できないものである。 全社活動に展開できた企業は早期に業績が回復し、競争力ある企業に体質強化ができる。 全員参加による全社的生産革新活動を展開するにはどのようにしたらよいか。 新商品を企画開発するには、営業部門が製品の市場性、価格、予測販売数量等を調査し、開発・設計部門が最短期間(納期厳守)で設計することが競争力ある製造会社の条件の一つである。 当然のことであるが、過去トラをDR・FMEAを活用して品質問題を未然防止した生産しやすい設計が求められる。製品の品質は設計品質で決定されるとしても過言ではない。 コスト競争力に勝つためには、開発・設計者は製造現場をよく理解していることが大切である。営業部門は特に顧客との情報を密にして受注情報の共有化を図ることである。 購買部門は100%品質保証され、低価格で「かんばん納入」ができるベンダーを選択する責任がある。部品の荷姿「通箱化」・収容数・品質保証方法等は購入仕様書で取り決め、輸送方法もルート便、業者便にするか決定する。 技術部門は製品仕様決定あたり、製品納入先との仕様取り決めは重要であり、納入荷姿・収容数等決定すべき事項がある。信頼性の高い品質で仕損費が発生しない工程設計は、製造手番「リードタイム」短縮の上でも大変重要な課題である。 途中工程の仕掛り在庫を最小限に抑え、直行率が高いモノ作りができることが価格競争に勝負できる企業となる。 生産管理部門は、営業部門との連携を強化し顧客の販売情報をいかに早く正確にキャッチし生産の平準化をするか最も重要な業務がある。 顧客の振れをいかに平準化生産するか、部材メーカーとの同期化とかんばんによる部材取り入れが生産革新活動を展開・拡大する中で大きな課題である。 設備技術部門は、設備で品質を保証できローコストでコンパクトな設備設計で、操作・保全性が良く故障の無い設備を製作すること、量産までに確実な生産準備ができることである。 工程設計段階では、いかに短く単純なラインを構築することが使命である。 特に重要なことは『設備で品質を作り込む』ができることである。 設備・装置産業では、PM教育も大切な業務である。 品質保証部門は、製造会社として全社員の品質意識高揚を図ることである。中でも品質異常が発見できるスキル教育と異常申告の吸い上げが機能していることである。 品質不良の未然防止活動とTPSに追従した品質管理手法の確立が重要である。 製造部門は縦流しラインを作り多能工者の育成、設備の日常管理ができるスキルの向上、生産指示かんばんにより工場全体が同期化した生産体制と『工程で品質を作り込む』品質保証の仕組みが出来上がっていることである。 総務部門は、TPSの啓蒙活動と人づくり、人材の適材適所配置、事務用品に至るまでの経費削減を全社活動に展開することである。 この様にどの部門でも、製造した製品を世界の市場に安定供給するには、生産革新活動を全社活動として展開することが最も重要である。 『全員が組織的に機能し、目標に実現に向かって智恵を出し自分の役割を果たしている』姿こそ生産革新活動が展開できている企業である。 革新活動とは『過去を捨て新しい企業文化を創る』ことである。 経営トップからオペレーターまで、真剣に革新活動を継続していることが企業発展の第一歩である。 この改革活動が会社方針管理に盛り込まれ計画的に展開され、実績を関心をもって評価する人が要ることが継続的改革の基になるのである。 顧客に信頼される企業を目指し 『自分で先ず実行する』、『体で覚えること』を実践することである。 以上 |
|||
|
|
|||
 「コンサルタントのひとりごと」 「コンサルタントのひとりごと」 |
 |
||
| 岩城生産システム研究所 岩城 宏一 | |||
― 全員参加による経営活動の薦め31― 経理部門の改革 トヨタ生産方式導入時、改善活動は主として生産現場を中心に進められる。そのような中で本社スッタッフの多くは、比較的覚めた目で傍観しているのが普通である。しかし経理部門は、この改革に非常に積極な反応を示す。 トヨタ生産方式を始める会社は、一般的に経営が苦しく、時には債務超過になっている場合も珍しくない。そのようなとき、外部の株主や銀行等の直接の接点である経理部門は、経営の苦しさを、身をもって受け止めている。そのため、経営収支の改善に関しては、強い関心をもち、またその成否についての鋭敏な識別感覚を持っている例が多い。 トヨタ生産方式へ移行のための改善が始まると、2〜3ヶ月で在庫や諸経費の減少が目立ち始め、収益の改善が決算上でも認められるようになる。さらに生産部門の改善が進行し、仕事の環境が整備されていくに従い、収益改善の動きは加速され、資金調達のための長年の経理部門の苦労は、徐々に氷解していく。 正しい手順による、トヨタ生産方式への移行時の個々の改善は、確実に収益を改善して経理部門を助ける。そのため、直接決算を担当する経理部門にとっても、トヨタ生産方式への転換は、重要な改善施策であり、生産現場と表裏一体になって改善活動が必要である。 実際の改善の着手の優先順位及び展開日程は、現地現場の情況及び決算上の緊急度より決定される。また改善活動は、月次または半期ごとの決算上の効果を追尾しながら、改善方法やその進度の適否を判断し修正または加速する。 従って毎月次の利益、外注費、輸送費、人件費、在庫金額、品質上の損失等諸項目の変化についての正確で迅速な提示は、生産現場の改善活動にとってはな指針であり、トヨタ生産方式への移行過程における、経理部門の大切な役割である。 トヨタ生産方式への移行が進み、全員参加経営活動が強まるに従い、経理部門は生産部門のみならず、全体の活動の成果を取りまとめ、評価資料として関係部署に提示する。それによって、全部門との連携を深めていく。 経理部門の実際の仕事は、通常の業務の他に、経営計画に設定された財務上の諸目標を達成するための、改善活動の事務局を担当する。即ち財務上の諸目標の起案や、月次や半期、年度等、適宜目標対比の成果を提示して、全体の活動をリードする。改善活動に参加している各部門は、当初設定した目標を実現するために、経理部門から提示された資料を基に、自らの活動を自己管理し、改善活動を展開する。 経営収益を損なった企業の財務の維持管理は、金融機関等からの借り入れや返済等に、非常に大きな労力と精神的な負担を強いられる。財務管理は当面の金策に奔走するのではなく、財務を健全化することに本来の働きがあり、それを実現のしないかぎり、言うまでも無くこの窮地から脱することは出来ない。 そのための活動の場は前述のとおり、金融機関等の外部ではなく社内にある。 即ち、全員参加による改善活動のもとで、財務を健全化するための必要な諸目標を設定して、その実現に向かって、各関係部署に適宜情報を提示しながら密接な連携を築き、自らが積極的にその活動に参加することである。 (以下次号) |
|||
| ■無断複製・転用・販売を禁止します■ Copyright©Iwaki Production Systems Research Ltd. 2005- |
|||