 |
発行者 岩城生産システム研究所 編集者 IPSインターナショナル |
||
| 平成19年09月15日発行 第050号 | |||
| ― 目 次 ― | |||
◆ 「抵抗勢力と呼ばれながら!」 しなの富士通 宮沢 賢一 様 ◆ 「コンサルタントのひとりごと 〜全員参加による経営活動の薦め30」 岩城生産システム研究所 岩城 宏一 |
|||
|
|
|||
 「抵抗勢力と呼ばれながら!」 「抵抗勢力と呼ばれながら!」 |
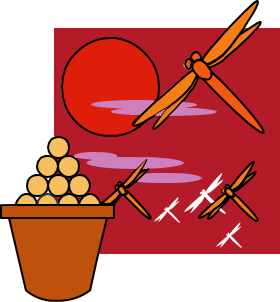 |
||
株式会社しなの富士通 第四製造部 製作課 宮沢 賢一 様 |
|||
私が初めて岩城先生にご指導を頂いたのは6年前で、最初に言われた言葉は「物が多い!流れが見えない!物はお金、あちこちにお金が眠っていますね。」であり、今でも鮮明に覚えております。 私の性格は、自分で納得しなければ行動もできないアイデアも浮かばない堅物(自称)であり、指導会のたびに岩城先生から思いもよらない指導・課題を頂き、納得できず毎回バトルがあったように思います。周りからも抵抗勢力との声も聞こえており、今回コラムに投稿しなさいと先生に言われ、何故?と思いましたが、私なりに改善にかける思いを投稿させて頂きます。 私たちの工場はクリーンルームである前工程と一般環境の後工程からなり、私は前工程に所属しています。前工程組立ラインの元の体制は、各装置の間をロボットでつないだ、大量生産をバッチ処理で行なうラインでした。私の業務は、各装置に流す製品を指示するいわゆる段取マンですが、工場は約八割が請負社員で構成されていて人員変動が多く、そのため作業指導や補助を行なうことがあり、毎日が戦争のようでした。 |
|||
| 改善活動を始める前は、当然の如く工場内には製品が溢れかえりあちらこちらに倉庫が幾つもあるような工場でした。ラインには、化成処理や熱処理、加工・冷却など処理スピードの異なる様々な工程があり、例えが違っているかもしれませんが、山手線の線路上を、電車だけでなく汽車や新幹線・バス、果ては自転車のような超ゆっくりのものが、各駅停車あるいは快速や特急など頻繁に運行している状態でした。この混流(混乱?)の前工程がやっと整備され流れができつつあります。 改善が進むに従い、路線がだいぶ整備され物の流れが明確になり、工程への指示も必要最低限になりました。何度も先生とのバトルはありましたが、路線の整備で工程内の物量(お金)が三分の一に減少した事は紛れも無い事実であり、自分の勉強不足のため未だに納得できない事もありますが、今後も自分なりに理解し活動を続けていきたいと思います。今の課題は、設備が連結されてライン化された各工程(駅)に到着する、乗り物の大きさ(車両編成数)をできる限り小さくし【目指すは1両編成】、更に段取り替えを増やすように挑戦中です。 |
 |
||
| しかし、熱処理などバッチ運行の駅の改善がまだまだ残っています。必要数に合わせる改善が必要ですが、製品の特性上、室温が数度変動しても不具合が生じてしまうデリケートな製品で、できたものの修理や調整ができないためミスが有れば製品は全て不良に繋がります。 ここでは不具合の早期発見・早期対処による直行率(不良率)の改善と、繰返し作業・標準作業などを進めることにより、作業ミスを改善できると信じて進めていこうと思います。 また更には、前工程と後工程は完全に壁で仕切られており別工場のようになっていて、情報がタイムリーに伝わってきません。急な数量の変動などでこの路線では都会の駐輪場のように、製品が滞留してしまう事もあります。中間ストアを有効に機能させ、定置・定量を徹底し、この渋滞を解消する事も課題です。言葉では簡単ですが、この路線に、後引きに基づいて前工程にしかける仕組み、と正確な運行の時刻表を作る事は大変なことです。執念深く活動していこうと思います。 今日までに投稿された方のコラムを拝見させて頂きましたが、他のグループは凄いな!うちはまだまだ足元にも及ばないなと思いました。私は負けず嫌いでもあります。この活動は一人ではできません。誇れる仲間(各工程のプロ・専門スタッフ)とともに活動を進め、他のグループに負けない工場に変えていきたいと思います。 岩城先生,松岡先生をはじめスタッフの皆様にご指導頂くことでここまで前進する事ができました。まだまだまともな時刻表もできておりませんが、今まで以上にご指導ご鞭撻を宜しくお願い致します。 以上 |
|||
|
|
|||
 「コンサルタントのひとりごと」 「コンサルタントのひとりごと」 |
 |
||
| 岩城生産システム研究所 岩城 宏一 | |||
― 全員参加による経営活動の薦め30― 即ち品質保証に関する全てを管理対象としていた“定常管理”を、保証のための仕組みを構築し、それに置き換えることによって、変更または異常時のみの “変更管理”や“異常管理”で対応することを指向する。トヨタ生産方式における、“異常があったらラインを止めろ”は、定常管理をこのような仕組みに置き換えることが前提になっている。 多くの企業の品質保証は、旧来の検査に依存しているのが実態である。そのため、先ずこの検査を、工程で品質を造りこむことに改めることが必要になる。 しかし、工程で品質を保証する方法に移行するためには、非常に多くの改善努力を必要とする。品質部門はこれを傍観するのでなく、その改善活動を主導し、さらに、自らの業務に内在する多くの問題を、改善しなければならない。 品質保証部は受け入れ検査や出荷検査等のため、検査対象の部品や製品を検査室へ持込み、品物の停滞を随所に発生させている。これは工場での4Mの変動を無くす上で重要な改善テーマである、トヨタ生産方式の“流れ”づくりの大な障害になっている。 通常は、流れ造りは生産現場の人達を中心に行われている。しかし、これ等の品物の停滞を無くし、流れを整備することは、新たな品質保証の仕組み造る上での重要な前提条件であるため、それは本来品質部門の人達の仕事である。 また流れが整備されるに伴い、一つ一つの検査項目の原因工程を特定し、その原因の解明、対策、維持のための条件管理の仕組みづくりは、検査を工程で、品質を造りこむための大切な仕事である。これは、地味で忍耐強い改善活動を必要とする。この活動に参加し、それを成功に導き、さらにはこれらを、会社全体の新たな品質保証の仕組みとして構築することも、品質部門の重要な任務となる。 従来は、どちらかといえば後追い的であった品質保証部門の仕事は、上述のように、会社全体の品質保証システムの改革や、後述の会社として設定した品質に関する諸目標の達成、さらには品質不良に対する予防保全活動の展開などの、能動的な活動に変わる。 そのため、品質保証の仕組み(システム)の構築後も、その運用管理またはただ単に番人に止まることになく、その仕組みの改廃、レベルアップに必要な改善活動に積極的に参加し、これをリードしていくこと大切である。 新たな品質保証体制に移行後の品質部門の実際の仕事は、既に述べたように“その部署の仕事の品質は、その部署の責任”、即ち自己責任を原則に、製造品質は生産現場が、設計品質は設計部門、部品の品質保証は購買部門の仕事になる。 これに伴い、多くの品質保証のための仕事が、品質保証部門から他の関係部署に移動する。そのため、従来の“品質に関することは何でも品質保証部”的な役割から開放されることになる。 特に品質保証部門の重要な仕事であった“検査”は、本来他の人に仕事をさせ、それをチェックする発想が根底にあるため、自発性、自己管理を前提とした、全員参加型の経営活動では、品質管理部門から“検査”業務は、多くの場合なくなる。 このように、会社全体の品質に関する業務が整理されてくると、品質保証部門の業務も分かりやすくなる。先ず、外部に対しては、顧客にたいしての品質上の窓口として、品質クレームの受付処理、また品質情報の収集等を行う。 社内では、中期、年度経営計画に取り上げられている、品質に関する会社方針、さらには品質管理に関する重点実施事項等の取りまとめ、及びその展開の事務局として、その活動を主導する。 要は、設定された会社目標を達成するために、各組織に分散された品質保証活動を支援し、全体として纏めることが任務である。しかしここで大切なことは、各組織を纏めるために如何に指示や命令を繰り出すか(これは従来のやり方)ではなく、皆が纏まる為に自らが如何に働くかである。 以上は品質保証部門の品質に対する経営管理的な役割であるが、その他に、多くの実務的な役割がある。例えば、新製品展開フローによる新製品展開の為の業務は、すでに述べたように新製品の業務の進行に従い、各関係部署が順次仕事を引き継ぎ、当然その引継がれた仕事の品質は、担当部署の責任で(例えば、部品品質は購買部門、製造品質は生産部門)保証されることになる。しかし全体を通しての品質の管理は、品質保証部門の責任になり、それを実行する(例えばシステム監査)為の仕組みを造りは重要な仕事になる。 また、生産現場では製造品質を保証する手段として、QC工程図を作成しそれを用いる。その工程図が、設計品質、部品品質の出来栄えや市場要求品質との関連で、十分に適合しているかの監査も品質保証部門の仕事である。 監査は、通常は強制的な意味合いを持っているが、ここでは、本来製造品質は生産部門の責任下にあるため、万全を期すため生産部門から監査を依頼する形で行われる。 以上は、全員参加型の経営に変わり、品質保証も“検査”から“品質を造りこむ”品質保証の体制に移行後の、品質保証部門の業務の概略であるが、大切なことは、これまでの品質管理をさせる立場から、各仕事の現場で品質か確実に管理されるために、自らの役割を掘り起こし、積極的にその責任を全うしていくことが求められる。 (以下次号) |
|||
| ■無断複製・転用・販売を禁止します■ Copyright©Iwaki Production Systems Research Ltd. 2005- |
|||