 |
発行者 岩城生産システム研究所 編集者 IPSインターナショナル |
||||||
| 平成19年03月15日発行 第038号 | |||||||
| ― 目 次 ― | |||||||
◆ 「トヨタ生産方式の楽しさと喜び」 FDK㈱ 櫛田 充 様 ◆ 「コンサルタントのひとりごと ~全員参加による経営活動の薦め18」 ㈱岩城生産システム研究所 岩城 宏一 |
|||||||
|
|
|||||||
 「トヨタ生産方式の楽しさと喜び」 「トヨタ生産方式の楽しさと喜び」 |
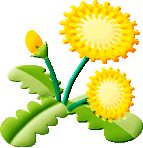 |
||||||
| FDK株式会社 モジュールシステム事業部 第一製造部第二製造課 櫛田 充 様 | |||||||
<はじめに:職場の紹介と私の役割> 私の職場は、FDK㈱いわき工場のSMTによるボードアッセンブリー工程です。 現在、SMTライン10ラインを有して、液晶テレビ用インバータモジュール基板や携帯電話用VCO(電圧制御発振器)基板の生産を担当しています。 私は、現在主にかんばん、ストア、みずすましの改善にチエと汗を流しています。当面の改善テーマはフロア内をスイ・スイと回れる20分みずすまし(従来はこの倍のサイクルでした)を回そうという目標に挑戦中です。 |
|||||||
<トヨタ生産方式との出会い> 「トヨタ生産方式を導入する」というトップ方針の下、岩城先生の初めての指導会が開催されたのは2004年1月6日のことでした。 第1回岩城先生指導会は、先生を中心に厚い厚い人の壁ができるような状況で、ご指導内容を近くで聞く事すら難しい状態でした。しかし、指導会終了後、即、指示が飛んできました。「まず、2Sを徹底的に行う!」ということです。 生産現場には、今、必要でないモノは置かない!必要なモノは必要な時に必要なだけ持ってくれば良いという先生の教えを受けての指示です。 全員で、ライン周り(特に壁際が大変な状況でした)に有る様々な物を取り払いました。棚・棚・棚・・・間接部門からも応援をもらいながら徹底して行いました。この結果、ライン内は見違える程スッキリしましたが、キレイにする |
|
||||||
| ことを重視したために、段取り替えの時には”てんてこ舞”の状態になりました。つい先ほどまでここに有ったモノが無いのです。(フロアの隅に追いやられている)。そのため、作業者からのクレームが多発するという事態が起きました。このクレームへは段取り専用台車(キャスター付) を作成することで解決しました。力の無い女性でも楽々運べるように工夫しました。 しかし、このときは、「これで本当に良いのか?なぜ、その場所で使用する物を、わざわざ工数を掛けて移動させなければならないのか?」という疑問が残っていたというのが本音でした。 その答えの一つが解ったのは、実はしばらく経って“みずすまし”を廻す段階まで来た時です。「あれれ!ライン脇にまっすぐな通路がある」・・・「そうか、こう言う事か」・・・ということでご指導の意味を実感し、理解できた事に喜びを感じた瞬間でした。 <なぜ、今のままではダメなのか?> トヨタ生産方式では「なぜ?」を5回繰り返し、最善の職場にしていくということがあります。 しかし、取り組みをはじめた当初は、トヨタ生産方式とは違う意味合いのなぜ?を繰り返していました。「なぜこれではダメなのか?」「今までのやり方でも問題無いじゃないか!なぜ変えなければならないのか?」という、できない言い訳を探すための「なぜ?」です。正直、この「なぜ?」を克服するのには数ヶ月もかかりました。上司からトヨタ生産方式の考え方や仕組みについての教育と皆で取り組んだ改善のための行動の積み重ねがあってのことでした。 実は、2004年1月の指導会開始当時の私は、SMT実装ラインの計画担当として日々の計画(製品投入計画、投入ライン計画、数量計画)を立案し、ホワイトボードを使って指示を出すという仕事を担当していました。それまではこうした仕事の仕方が常識であり先輩から受け継いだ手法だったのです。それが、突然、“ホワイトボードにまで撤去命令”がだされ、変わりに“かんばん”と“みずすまし”で生産するように・・・ということになりました。そして以降の指導会でも、それまでの仕事の積み重ねに対しことごとくダメ出しをされるという状況が続きました。私自身の混乱の始まりです。しかし、悩みながらも、とにかくやってみるということを積み重ねました。非常に苦しかった時期でした。 そのうち、部品一点一点に“かんばん”が付き、後工程ともかんばんでつながるようになると、飛躍的に改善がすすみはじめました。ある日の指導会(岩城先生、佐藤先生、杉本社長をはじめとした会社幹部、そして指導会参加者が何十人もいる)では、みずすましのルートを実際に係長が歩き、そのルートや時間を全員(何十人もが)で確認するというようなことも経験しましたが、工夫の積み重ねにより“ゲンゴロウ”が“みずすまし”に変わりはじめ、本当に工程間のモノと情報をつなぐようになり始めると更に改善が進みました。 昨年6月の指導会では、それまでの改善の積み重ねやSMTラインの生産性改善(外注に委託していた仕事の社内取り込み)、新しい仕事の内製化をご報告した時に、係長以下スタッフ全員に対して岩城先生よりお褒めの言葉をいただくまでになりました。 10人いれば10の意見が有るようにトヨタ生産方式を完全には理解していない意見も中には有ります。しかし、全力で改善に取り組もうとする人は確実に増えています。 一人一人の気持ちが統一され、目標に向けて努力すれば、結果は自ずと付いて来るものと確信しています。これまでの私たちの職場がそのことを実証していると思います。 <活動をはじめて3年、更に大きなカベに立ち向かう> 私たちの活動は、今でこそ大きな成果につながっていますが、とても順調に進んできたとは言いがたく、現在でも多くの問題を抱えています。 最大のものは、いまだ切り崩せぬ大きな壁・・・平準化生産への対応です。 生産の平準化が図られ後引き生産ができている製品もありますが、その一方で激しい受注変動により大きくあばれている製品もあります。これが現在の最大の悩みです。 但し、2年前と違うのは、各個人がこの間に確実に知恵を身に付けたということです。トヨタ生産方式の大事な要素である「なぜ?」を追及していける人が大勢いるということです。 心を一つにして、前向きに進めば「平準化生産」への壁も乗り切れると確信しております。3年のご指導で大きな財産を頂いている人が沢山いるのです。 私自身まだ初心者ながら、これから先まだまだ出るであろう問題に対して真正面から取り組んでいきたいと考えます。 |
|||||||
|
|
 2007年1月11日杉本社長賞を受賞 表彰式には岩城先生・佐藤先生にもご同席いただきました |
||||||
|
|
|||||||
 「コンサルタントのひとりごと」 「コンサルタントのひとりごと」 |
 |
||||||
| ㈱岩城生産システム研究所 岩城 宏一 | |||||||
|
|
|||||||
| ■無断複製・転用・販売を禁止します■ Copyright©Iwaki Production Systems Research Ltd. 2005- |
|||||||
