 |
発行者 株式会社岩城生産システム研究所 編集者 有限会社IPSインターナショナル |
|
| 平成18年10月15日発行 第028号 | ||
「岩城生産システム研究所NEWS」第28号を発行させていただきます。 今回はNEC関西・西田 明弘 様及び、弊社・岩城 宏一のコラム「全員参加による経営活動の薦め8」を掲載させていただきます。 どうぞ宜しくお願い致します。 業務部 |
||
|
|
||
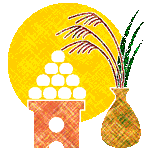 |
||
| NEC関西 化合物デバイス部 西田 明弘 様 | ||
私は化合物半導体の拡散ラインの工程管理をしております。当社の化合物拡散ラインは岩城先生から生産革新をご指導 戴いて5年目となります。 この間の数多くのご指導会を通じて得られたことを、自分なりに一言で表現すれば、表題の文字になる気がします。 最初に小さくしたのは、1ロットの構成枚数(ロット枚数)を1/4にしたことです。 先生のご指導があってからこれを実施するには、もちろん私を含め多くの抵抗勢力がありました。ご承知のごとく半導体製造 では設備が高価なため、設備を遊ばせないように効率よく稼動させ最大のアウトプットを出すことが重要でありますので、ロッ ト枚数を小さくすることは設備負荷・作業工数・運搬工数が増えるなど従来の我々の常識からは正反対の考え方でした。 他ラインが小ロット枚数の実施を躊躇している中、当ラインが最初にこれに踏切ったのは生産革新をキックオフしてから5ヶ 月が経過した2002年9月、我々の最初の生産革新が始まりました。 最初は先生のご指導内容を半信半疑で、やってみて ダメなら元に戻せばよいという気持ちがありました。やってみると当然のごとくあちこちから不平不満が噴出しラインは混乱し ました。 ところが、2ヶ月も経過すると小枚数のロットは作業時間が短いため、作業待ちも短縮されLTが1/2になりその分ラインの仕 掛が減ったことで、心配した工数増はそれほど気にはならなくなりました。さらに図らずも、品質情報が早くフィードバックされ るようになり歩留が向上しました。結局、小ロット枚数は元に戻れなくなりました。 次に小さくしたのは、流れつくりに取組んだ後の、みずすましのサイクルタイムでした。 これは、2005年12月にトヨタの張副会長(当時)に当ラインをご視察戴いた際のお言葉から始まりました。 「30分間隔でみ ずすましが運んだら?」というコメントに、「えっ?」と言う声が思わず小さく出てしまいました。みずすましのサイクルタイムは 平準化した生産量から数時間間隔としておりました。まして一旦設備に掛かれば数時間出てこない工程がある中で、30分 間隔が必要であるのかと考えました。でも今から考えると、この時おそらくラインを見て瞬時にまだまだ仕掛が多いとお感じ になったのだと思います。 このサイクルタイムを小さくすることは試行錯誤の上みずすましルートの変更等も伴いましたが、さらに仕掛が減り生産革新 取組み当初からするとLTが1/3に短縮されました。のちに、これはみずすましの動きそのものが心地よいリズムなのかなと 感じております。 現在は、さらにロット枚数を小さくし、サイクルタイムも小さくすることに取組んでいます。 当ラインではこの2つを小さくすることが大きな成果に結びついていることをまさに実感しております。でも本音では、大変 な世界に踏み出したなとも感じております。 しかし、「ここまで来たら後戻りはできない。 新たな次元へ向かって先へ進むだ けだ!」と思いつつ、次なる困難も心地よく変えられるように生産革新活動に取組んで行きたいと思います。 以上 |
||
|
|
||
 |
||
| ㈱岩城生産システム研究所 岩城 宏一 | ||
― 全員参加による経営活動の薦め8― |
||
不規則な仕事の振れは、仕事の当事者にとっては、大変大きな負担を強いることになります。 特に納期がまじかにに 迫った仕事の量が当事者の能力をはるかに超えている場合など、また逆に在庫調整のため生産が止ることなどは、生産 現場に大変な混乱を招くものです。もしこのような振れがなくなれば、生産は大変楽なものになります。 このような生産の振れは、市場の実際売れ行きの変動よりは、販売を見越して前もって造り溜めをしたり、一度にまとめ てつくる等の、作為的な操作によって発生する場合が多く、このような振れの方が、実際の販売の変動よりは何倍も大きい のです。 従って、市場で売れるものだけを、その場で造って届ける、即ちトヨタ生産方式のジャストインタイム、必要なものを必要な 時に必要なだけつくるということは、この作為的な過大な振れを防ぐ上で大変効果的な手段になっています。 しかも、その売れを溜めないで、売れたらその場で造くれば、売れの変動量はその分だけ小さくなります。 “小さく仕掛 け小さく造る” トヨタ生産方式での少量生産は、結果的にこの変動量を小さくしていることになります。 この変動量が小さくなれば、少量の在庫(トヨタ生産方式では店)によってこの変動を完全に吸収することができ、それに よって生産現場は、いつも安定した生産を続けることが出来ることになります。これが生産の平準化の仕組みであります。 生産が平準化されると、生産活動は大変容易になり、生産性や品質が圧倒的に向上し、さらには納期の遅延などは完 全になくなってしまいます。 それはトヨタ生産方式に変えることによって、実際の生産現場に次のような変化が起こる ためです。 一つは生産現場の皆が、後工程からの引き取りによって、今何を造らなければならないかが、上司に指示されなくても常 に分かっており、その通りに働くことが出来ること。 第二は生産の変動がないため、人々の動作が繰り返されるため人々の スキルは向上し、連動した各の職場間および職場内の人々が、お互いに連携しやすくなることであります。 さらにこの連動は工場内に留まらず、市場の販売店から工場、工場から部品、資材の供給先までと、生産時品物が移動 する全域に広がっていきます。 このことによって、品物を販売しそれを生産するための全ての工程や人々が連動し、あたか も大きなプラント装置のように、自動的に同期して動くようになります。 それに伴い生産現場では末端の市場で品物が売れると、その品物の移動が上流工程へと伝播し、連動する全ての工程が 働き始める。それによって生産された品物は、先に売れた品物を補充し次の売れに備える。 このよう、トヨタ生産方式に移行後は、全体工程や人々が自動的に稼動するため、極めて機械的に生産を行うことができ、 それは従来のように生産管理部門によって生産指示が出され、その指示に従って動いている生産現場とは全く異質なもの であります。 このように生産管理部門などの生産指令によって、管理された生産現場から全体が後工程からの引き取りに連動して、 全体が同期して自動的に動くことを“自働化”と呼んでおり、トヨタ生産方式の働きを間接部門に取り入れる上で、最も大切な 要素であります。 “自働化”はトヨタ生産方式への移行による、生産の平準化と小刻みなジャストインタイムが、その大前提になっています。 ではこの“自働化”を生産現場以外の所謂間接部門に移植するならば、どのような問題と効果を予測することができるのか 以下に検討してみましょう。 (次号につづく) 以上 |
||
| ■無断複製・転用・販売を禁止します■ Copyright©Iwaki Production Systems Research Ltd. 2005- |
||