 |
発行者 株式会社岩城生産システム研究所 編集者 有限会社IPSインターナショナル |
|
| 平成18年09月15日発行 第026号 | ||
「岩城生産システム研究所NEWS」第26号を発行させていただきます。 今回はNECパーソナルプロダクツ・佐藤 直子 様及び、弊社・岩城 宏一のコラム「全員参加による経営活動の薦め6」を掲載させ ていただきます。どうぞ宜しくお願い致します。 なお、9月19日(火)は弊社事務所を臨時休業とさせていただきますので、ご了承下さいますようお願い申し上げます。 業務部 |
||
|
|
||
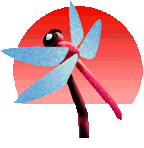 |
||
| NECパーソナルプロダクツ㈱ テープストレージ事業部 生産部 佐藤 直子 様 | ||
NECパーソナルプロダクツの佐藤直子と申します。今回、水野様よりコラムの件お話頂きました時、冗談を仰っているのかな と思っておりました所、正式にご依頼を頂き大変恐縮しているところです。何からお話させて頂いたらいいのか相当迷ったの ですが、今夏の甲子園熱戦から初心に帰る事の重大さを学びましたので、先生のご指導会に初めて参加させて頂いた時の 事からお話させて頂きます。 もとより個人の改善活動が好きだった私は、ちょうど5年前、岩城先生がご指導される姿を米沢で拝見し、私もあの行列に 参加してみたいなと思い、上司に頼み込んで新潟のご指導会に参加させて頂きました。ご指導会当日、ホテルのレストラン で先生と渡邉TMとお会いしご挨拶させて頂いてから早5年の月日が流れてしまったんだなと、このコラムを執筆しながら感慨 深くなりました。 さて、当日の新潟ご指導会は、私にとってまさに「晴天のへきれき」。雷に打たれたような強烈な印象が今でも瞼の裏に焼き 付いています。今迄の自分の改善活動を遥かに超越した、神がかりのようなご指導に心打たれた日でした。中でも、先生が “L/Tの長いものは内製化しなさい”と仰った時には“え???”何の意味か当時の私には理解できませんでした。それが、 今や内製化(色んな意味で)がどんどん進み、見る間にNECは変革して行ったように思います。これも、先生の時には優しく 時には厳格に叱咤激励して下さったお陰なのだなと最近つくづく感じるようになりました。近頃では、かんばんや平準化、 ルート便や標準作業等の言葉が通常の言葉となって職場の中から聞こえてくる迄になりました。まだまだ完全に浸透しきった 訳ではありませんが、これから先、改善活動をグループ員と進める中で、何事にも新鮮な気持ちで接し、その事に常に疑問 を投げかけながら一歩一歩推進して行きたいと思います。 最後になりますが、私が先生の仰る言葉の中で一番安心する言葉を書いて終わりにしたいと思います。 『 そぉう。そぉう。そぉう。 』・・・この言葉は、自分たちが改善を説明した後に、わかったその通りと言う意味だと自己解釈 しています。 岩城先生、岩城生産システム研究所の皆様、これからも末永くご指導下さいますようお願い致します。 以上 |
||
|
|
||
 |
||
| ㈱岩城生産システム研究所 岩城 宏一 | ||
― 全員参加による経営活動の薦め・6― |
||
3、組織と運用方法の特徴 トヨタ生産方式は、普通の生産仕方とは生産現場の構成(組織形態)とその運用方法が異なり、両者はまったく違ったもの であります。その違いはトヨタ生産方式の三本柱である「ジャストインタイム」「自働化」「生産の平準化」に象徴されます。トヨタ 生産方式の最も大切な部分である基本的な機能を理解するために、この三つの特徴について以下に説明します。 先ずジャストインタイムは一般的には、“必要なものを、必要な時に、必要なだけ”と言われています。しかしこれはあまり にも大まか過ぎて、具体的なことは良くわからないのが実情でしょう。そこで実際の生産現場の活動に即してより具体的に 見てみると、“ジャストインタイム”とは“後ろの工程が必要なものを、必要な時に、必要なだけいつも前工程は造り続ける ということになります。“後ろの工程”とは各工程の直ぐ後ろの工程ということであり、さらに後ろの工程に向かって追っていく と、当然のことながら最終的には、お客様ということになります。 このことを工場単位でみると、工場の最終出荷工程は、お客様が“必要なものを、必要な時に、必要なだけ”つくり続けると いうことになります。最終出荷工程がこのようにお客様にジャストインタイムに品物を送るためには、これに隣接するその前 の工程が、最終工程に対しジャストインタイムに作業しなければならいことになります。 さらにその前工程へと上流工程へ向かって連鎖し、結果的にはお客様から工場の中を通り、さらに部品供給先までの品物 が移動する全域に亘り、ジャストインタイムの動きを連鎖して、はじめてジャストインタイムが、実際の生産行為として成立 することになります。 では通常の生産では、このジャストインタイムはどのようになっているのでしょうか?ご存知のように、通常の生産では 生産計画で各工程は動いていますが、その計画が工場の出荷日から逆算し、後工程に品物を切らさないように、各工程の 生産日程を決めている為、大まかな意味でジャストインタイム生産していることは変わりありませんが、少し踏み込んで調 べてみると、両者の違いは一目瞭然であります。 先ず通常の工場では、その間に設けられた倉庫、またはそれに類するデリバリ拠点等が後工程になり、直接お客様では ありません。また“必要な時”の限定が、トヨタ生産方式の場 合は、“今すぐ”または“次の引き取り便が来るまでの 間”のように分単位または時間単位で、非常に短くまたその引取り間隔が正確に守られているのに対し、通常の工場では この“必要な時”の限定が、特別な場合以外は、今月中、今週中等のように極めて曖昧であります。 例えば、工場は来月販売するものを今月生産して倉庫に納める等は、最も普通の生産の仕方であります。この場合、工場 は月単位の“必要な時”の中で生産していることになり、工場内の各工程もそれのゆっくりとし時間の流れの中で、一週間 単位または早くても一日単位を“必要な時”として生産していることになります。これは組織活動上、重要な影響をもたらすし、 “必要な時”の曖昧さは、実はその組織の中の人々の動き、または働きの曖昧さをもたらしていることになります。このことは 私たちは日常の生活の中でも良く体験することであり、約束の期限の直前になって、慌てて間に合わすなどその好例でありま しょう。 このように、トヨタ生産方式と通常の生産では、ジャストインタイム即ち必要とする時間の限定がまったく違ったものであり、 トヨタ生産方式ではその時間の間隔が大変短く、また設定された時間の遵守が厳格であります。 確かにこのように時間に対し、厳格になればなるほど仕事の効率は向上する。反面それは仕事の強要であり、労働強化 そのものではないかと抵抗したくなる。しかし、実際はジャストインタイムに対する時間間隔、即ちサイクルタイムが短く正確 (厳格)なほど、トヨタ生産方式では仕事を楽にまた間違いなく、続けることが出来るのであります 。この点が私たちが注目 すべきトヨタ生産方式の大切な機能であります。 (次号につづく) 以上 |
||
| ■無断複製・転用・販売を禁止します■ Copyright©Iwaki Production Systems Research Ltd. 2005- |
||