 |
発行者 株式会社岩城生産システム研究所 編集者 有限会社IPSインターナショナル |
|
| 平成18年1月5日発行 011号 | ||
| 謹 賀 新 年 | ||
新年 明けましておめでとうございます。 旧年は大変お世話になりました。 本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 さて、「岩城生産システム研究所NEWS」第11号を発行させていただきたいと思います。 今回も前回に続き、富士通コンポーネント株式会社 取締役 手島 正行 様より頂戴いたしましたコラムを掲載させていただいております。 業務統括部 |
||
|
|
||
| 富士通コンポーネント株式会社 取締役 手島 正行 様 |
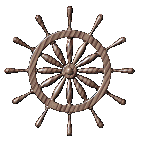 |
|
日本の製造業が変わり始めている。 ITバブルの崩壊を挟んだ10年、自信を喪失した多くの企業が復活を遂げる一方、『勝ち組』と『負け組』とが明確に峻別され はじめた。バブル崩壊が契機となったリストラと成果主義の徹底、工場売却と中国への急速な製造シフトをマスコミ・評論家 はこぞってパラダイムシフトともてはやした。 しかし皮肉にも、脅威の回復を遂げた『勝ち組』の多くが、この『大きな流れ』の 中で最後まで主役を演じつづけていたわけでない。 むしろ卓越した経営者は『原則に戻る』という単純で勇気のいる決断を 行ったのではないかと思われる。 この10年、経営者の多くは目の前にかけられた『梯子』を盲目的かつ効率的に駆け上ってきたが、ここに来てようやくその 『梯子』が本当に正しかったかどうか問い直す余裕をもつ一方、『勝ち組』と呼ばれる経営者は途中で梯子を架け替えていた のではないだろうかと思われる。 実際今となって見比べれば『勝ち組』と『負け組』は単に同じビルの違う階にいるのではなく、全く異なったビルに登っている ことに気づかされるのである。 現在、日本の経営インテリジェンスを代表する多くの紙面には、数年前の『中国進出礼賛』にかわり『生産革新』や『トヨタ 方式』の文字が乱舞する。 「無駄取り」と「効率化」のブームは製造業に限らず、サービス業や官庁にまで及んでいるが、 その成功の数倍もの失敗事例が書面を飾っているのも事実である。 なぜなら、従来から「無駄」や「非効率」を許容した 生産方式や経営指南書などなかったし、リストラや成果主義、製造現場の中国移管は「選択と集中」「事業の水平分業」の 名の下に行われた無駄の排除と効率化の最も先鋭的施策の筈だったからである。 一方、『勝ち組』と言われる企業の経営マインドをみれば、実に奇妙な展開を見せている。 多くの企業がつい最近まで時代遅れとさえ揶揄された『ものづくりへのこだわり』を究め続けているように見えるのである。 日本的経営の遺物とまで冷笑された垂直統合的『ものづくり』を復古・徹底しつづけているのである。 設計の標準化や製造 の一貫性は言うに及ばず、金型製作の内製化から製造装置まで自前で作り出す徹底振りである。 それは90年代を席巻 した経営ノウハウにおいては最も非効率なリソースの活用のひとつであったはずである。 しかし現実は、絶え間なく変化 する消費者マインドに対し最も効率的な資源活用であり、TIME TO MARKETのアプローチとなっているのである。 その実現のためには、マーケット・商品・現場を支える営業・設計・オペレータだけでなく、組織のあらゆる階層が最大の 出力を発揮しなければ実現できないシステムとしての総合力が問われるのである。 「現場・現物主義」という標語が、『勝ち組』の多くで語られるのは偶然ではないであろう。 また、その多くの企業が『人材の育成』という、更に大きく長大な目標に向かって認識を新たにしているのも興味深い。 人材は「横取りして利用する」のではなく「育てて生かす」ものであるという、本来あるべき姿を目指そうとしているように 見えるのである。 14世紀、イタリアに興り全欧州に展開した「ルネサンス」は、《再生の意》として知られ、ギリシア・ローマの古典文化を 復興し欧州近代文化の基礎となった学問上・芸術上の革新運動である。 その意味で現在、多くの『勝ち組』で標榜されている『生産革新運動』とは、むしろ『生産ルネサンス』『経営ルネサンス』と 呼ぶのが相応しいのではないかと思うのである。 以上 |
||
|
|
||
| 岩城生産システム研究所 代表取締役 岩城 宏一 |
 |
|
―勘違いの無駄・1― |
||
| 皆さん明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。また皆様の益々のご健勝をお祈り申し上げ ます。 さて去年は、トヨタ生産方式でよく話題になる、いわゆる“無理、無駄、むら”から”無駄もいろいろ”について、話題を取り 上げてきました。 その中で“無理・無駄・むら”は、現在行われている仕事、または動きの中にある“無理・無駄・むら”を問題 にしているが、視点を変えてみると、その仕事や動きそのものが、すでに無駄なものであることを指摘しました。 当然のことながら“無理・無駄・むら”取りよりは、その仕事や動きをそっくり止める事の方が、改善の効果は遥かに大きい ことは言うまでもありません。 何も疑問を持たないまま、無意識にそれが正しとしていることについて、改めて新たな視点で 見直さなければならない問題が、私たちの身の回りには沢山あることに気付きます。 これらの問題の多くは、誰かがちょっとした発言やきっかけが、いつの間にか世の中に広まり、それが世の中の常識になっ てしまったのでしょう。 しかもそのような発言やきっかけは、間違ってはいないまでも、ものごとの本質に根ざしたものより、 皮相的な着眼や思い付きが多く、また受け入れる側も、自らの諸環境との融合を十分顧慮することなく、安易に追いかけて いる場合が多いように思います。 例えば去年話題にしたように、“最新鋭の設備を買った”とか“設備を止めたら大変”なども、 その小さな例であろう。 最新鋭の設備は最大の武器と思うのが普通の人情であり、また設備を止めたら大変と思うのもまた、正常な常識である でしょう。 しかし最新鋭の設備を買ったため、それが大きな負担になり、また設備を止めないために、大きな無駄を発生 させていることも事実である。 要はその場の状況によって、様相がまるで違ったものになってしまいます。 私たちの身の回りには、このような皮相的な着眼や思いつきによる行動が、多くはびこっています。 その大きな理由の 一つは、その場の状況に応じて、それらを適正に対処していないことであり、結局人々の行動が “現地現物”から遊離して いることにあるように思う。 ここ数年来マスコミを沸かせた“選択と集中”“中国は世界の生産工場”“持たない経営”“規模の拡大”等々、それによって 功を収めた企業より、損失を増大させた企業の方が、何倍も多いことが、今になってみるとはっきりしてきているように思う。 これらはいずれも皮相的な着眼や思いつきで走った結果であり、私には「勘違いによる無駄」としか思えない。これらの無駄 は途方もなく大きく、会社そのもの存在を左右している。 本年度は、この途方もなく大きな無駄である「勘違いによる無駄」について、私の日々の生産革新の旅の中で遭遇する、 さまざまな話題を取り上げていきたいと思います。 |
||
| ■無断複製・転用・販売を禁止します■ Copyright © Iwaki Production Systems Research Ltd. 2005- |
||