 |
発行者 株式会社岩城生産システム研究所 編集者 有限会社IPSインターナショナル |
|
| 平成17年8月1日発行 002号 | ||
先月に引き続き、「岩城生産システム研究所NEWS」第2号を発行させていただきます。 どうぞよろしくお願い致します。 業務統括部 |
||
|
|
||
| 上席コンサルタント | 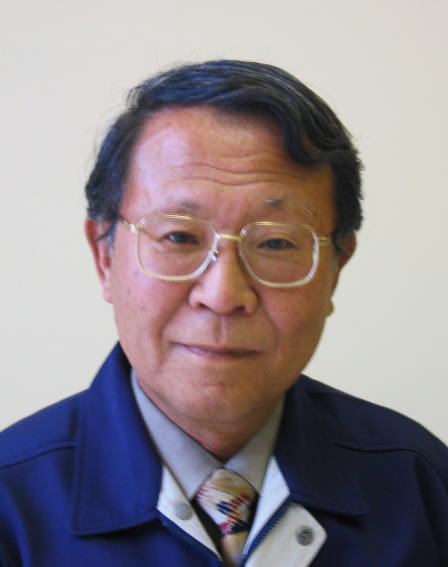 |
|
― 人づくりとトヨタ生産方式 ― |
||
一般に人生においての一大事業はマイホームを建てることと言われているが、企業においては安定した経営に改善する ための一つとしてトヨタ生産方式を導入することは、その企業の一大事業であると思う。 トヨタ生産方式を導入する過程においても、その成果を得られ始める。 そこでは一般的な生産方式の短所が浮き彫りになることが多い。 現行の生産方式でできる範囲でトヨタ生産方式に近付けようと着手するからである。 導入に着手するためには、より多くの部署の関係者が、各自担当する業務を自らの手で改善する・・・自分の職場の改善 は自分が主役で推進する。 人は保守的で、現在の生産方式、加工・組立方法等の環境を変えることに足踏みをする。 これを打破し、自らの意思で改善を継続していくことが人材の育成につながっていく。 企業における経営資源の第一は人材である!!と言われている。 特に製造業においては、この活動を通し、人の成長に従い、改善のスキルアップを図ることができる。 一般的には、生産管理部署(生産管理・工務・購買・営業)は、社内・外の物流改善(製品物流・調達物流)を担当し、製造・ 生産技術部署は、工程改善・設備改善と工程内の部品供給・製品の多回引き取りの仕組みを担当する。 改善の進め方は、工場全体にわたって展開する。 重点ラインを定め、そこを改善して、その成果(改善手法)を横展開する手法があるが、この改善では、限定された人しか 参加できず、多くの人たちの参加が遅れるため、成果には結び付かないことが多い。 全ての改善は遅行拙速、出来栄えが悪くとも、早く実施することが関係者のスキルを上げ、会社としての成果に結び付く。 加工ライン・設備の改善はあるべき姿を描き、特徴ある改善をすることにより、ノウハウが蓄積され、スキルも向上し、「オレ のつくったライン」 ・・・ 楽しい改善になる。 生産の仕組みは従来からの押し込み方式から、引きの世界に変えることである。 調達物流は生産の平準化をベースに店・かんばん・輸送手段(ルート便)を整備してサプライヤーに引き取りに行く。 これにより、関係者は日時のデリバリー管理の仕事から解放される。 構内及び工程間は、みずすましによって定時運行することにより、工程間を同期させ、仕掛り在庫を減らし、生産のリード タイムを短くすることができる。 各工程が縦持ちになり、短時間の段取替えが可能になると、簡単な仕組みで運用することができる。 この仕組みをつくるためには工程の全てを知り、顧客に対し、買いだめを止めて毎日納入の協力をお願いし、購入先に 対しては、平準化された生産部材を毎日取り入れする仕組みの確立が必要である。 トヨタ生産方式導入後においても、仕組みも工程も日々改善を継続する会社が、トヨタ生産方式を実施している会社と言われ ている。 以上 |
||
| ■無断複製・転用・販売を禁止します■ Copyright © Iwaki Production Systems Research Ltd. 2005- |
||